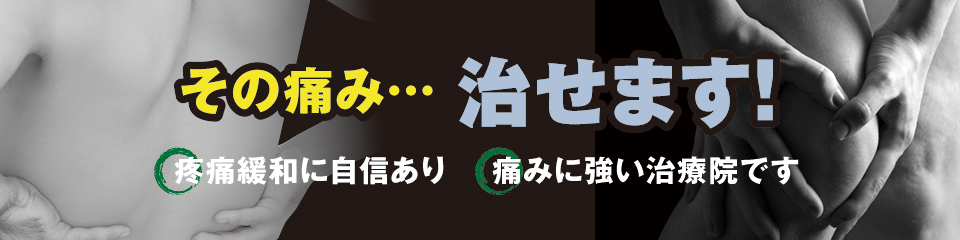2025年03月04日 [からだのこと]
読書好き
お疲れ様です。院長です。
3月4日の火曜日でございます。
今日は、「三線の日(さんしんの日)」だそうです。
では元気にネタいきましょう。
なんでも、読書好きな人は脳の構造が違うんだとか…。
言葉の理解と音の処理能力が高いことが判明したそうです。
最近本を読む人が少なくなっている傾向があるそうですが、読書をする習慣がある人とない人では、脳の構造に違いがあることが最新の研究で明らかになりました。
特に、言葉の意味を理解したり、音を処理したり、人の心を読み解く能力において、読書好きな人は優れた特徴を持つそうです。
研究者たちは1,000人以上の脳データを分析し、読書能力と脳の特定部位の関係を詳しく調査しました。
その結果、左脳にある言語や音声に関連する部位が読書の得意さと深く関係していることが分かったそうです。
楽しみのための読書をする人の数は世界的に見ても減少傾向にあります。
最近の英国での調査によると、成人英国人の50%は定期的に本を読まないと答えていて、2015年時の42%から増加しています。
また、16〜24歳の若者の4人にひとりは一度も本を読んだことがないという結果も出たそうです。
この変化が私たちの脳や進化にどのような影響を与えるのでしょうか?
人が長い文章を読むよりも映像のほうを好むことは、私たちの脳や人類の進化になにか影響を及ぼすでしょうか?
スウェーデン、ルンド大学の言語学・神経科学の専門家ミカエル・ロール氏が、1113人の脳データを分析し、読書能力と脳の特定部位の関係を詳しく調査しました。
その結果、読書家は脳の解剖学的構造にはっきりした特徴があることを発見しました。
言語にとって極めて重要な左脳のふたつの領域構造が、読書の得意な人の場合、明らかに異なっていたことがわかったそうです。
1.側頭葉前部:情報の関連付けや分類
まず最初の領域は側頭葉前部です。
左の側頭極はさまざまなタイプの意味ある情報を分類し関連づける場所です。
例えば、「脚」という単語の意味を組み立てるために、脚がどのように見え、どのように感じ、どのように動くのかを伝える視覚、感覚、運動の情報をこの部位が関連づけます。
2.横側頭回(ヘッシェル回):音声や言語の音を認識
もうひとつの部位は横側頭回(ヘッシェル回)です。
この部位は聴覚皮質(脳のもっとも外側の皮質)がある側頭葉上部のひだのことです。
横側頭回は聴覚野が存在する部分で、言語の音を認識する基盤となります。
読書は視覚的なスキルと考えられがちですが、文字を音と結びつけるためには音の認識が重要となります。
特に幼少期の読書能力の発達には音声の理解が欠かせないと言われています。
左横側頭回が薄いことは、重度の読書障害を伴う失読症と関連づけられてきました。
失読症の人とそうでない人との違いを単純に決めつけるものではありませんが、聴覚皮質が厚いほど読書が得意であることはわかっています。
では、聴覚皮質が厚ければ厚いほどいいのでしょうか?
たいていの人は左半球の聴覚皮質にはミエリン(髄鞘)がよりたくさんあります。
ミエリンは神経線維の伝達速度を高め、脳内の情報処理を迅速化する役割を持ちます。
このミエリンの影響で、左脳の皮質は薄くても広がりがあり、高速かつ正確な言語処理が可能になると考えられています。
一方で、情報を統合するような複雑なスキルには、より厚い皮質が有利とされます。
左側頭葉前部の厚みがその例で、この部分では、さまざまな情報を総合的に処理するために、神経細胞の重なりが多いと考えられています。
脳は「皮質可塑性」と呼ばれる柔軟性を持ち、新しいスキルを学んだり既存の能力を鍛えたりすることで変化します。
例えば、語学を集中的に学んだ若者は、言語に関わる脳の部位が厚くなることが分かっています。
同様に、読書も脳の構造を変え、特に左横側頭回や前側頭葉前部を強化する可能性があるわけです。
読書離れが進むことで、私たちの世界を理解する能力や、他者の心を読み解く力が失われていくかもしれません。
本を読む時間は単なる個人的な楽しみではなく、人間の知性や共感を育む大切な行為だと言えるでしょう。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
3月4日の火曜日でございます。
今日は、「三線の日(さんしんの日)」だそうです。
では元気にネタいきましょう。
なんでも、読書好きな人は脳の構造が違うんだとか…。
言葉の理解と音の処理能力が高いことが判明したそうです。
最近本を読む人が少なくなっている傾向があるそうですが、読書をする習慣がある人とない人では、脳の構造に違いがあることが最新の研究で明らかになりました。
特に、言葉の意味を理解したり、音を処理したり、人の心を読み解く能力において、読書好きな人は優れた特徴を持つそうです。
研究者たちは1,000人以上の脳データを分析し、読書能力と脳の特定部位の関係を詳しく調査しました。
その結果、左脳にある言語や音声に関連する部位が読書の得意さと深く関係していることが分かったそうです。
楽しみのための読書をする人の数は世界的に見ても減少傾向にあります。
最近の英国での調査によると、成人英国人の50%は定期的に本を読まないと答えていて、2015年時の42%から増加しています。
また、16〜24歳の若者の4人にひとりは一度も本を読んだことがないという結果も出たそうです。
この変化が私たちの脳や進化にどのような影響を与えるのでしょうか?
人が長い文章を読むよりも映像のほうを好むことは、私たちの脳や人類の進化になにか影響を及ぼすでしょうか?
スウェーデン、ルンド大学の言語学・神経科学の専門家ミカエル・ロール氏が、1113人の脳データを分析し、読書能力と脳の特定部位の関係を詳しく調査しました。
その結果、読書家は脳の解剖学的構造にはっきりした特徴があることを発見しました。
言語にとって極めて重要な左脳のふたつの領域構造が、読書の得意な人の場合、明らかに異なっていたことがわかったそうです。
1.側頭葉前部:情報の関連付けや分類
まず最初の領域は側頭葉前部です。
左の側頭極はさまざまなタイプの意味ある情報を分類し関連づける場所です。
例えば、「脚」という単語の意味を組み立てるために、脚がどのように見え、どのように感じ、どのように動くのかを伝える視覚、感覚、運動の情報をこの部位が関連づけます。
2.横側頭回(ヘッシェル回):音声や言語の音を認識
もうひとつの部位は横側頭回(ヘッシェル回)です。
この部位は聴覚皮質(脳のもっとも外側の皮質)がある側頭葉上部のひだのことです。
横側頭回は聴覚野が存在する部分で、言語の音を認識する基盤となります。
読書は視覚的なスキルと考えられがちですが、文字を音と結びつけるためには音の認識が重要となります。
特に幼少期の読書能力の発達には音声の理解が欠かせないと言われています。
左横側頭回が薄いことは、重度の読書障害を伴う失読症と関連づけられてきました。
失読症の人とそうでない人との違いを単純に決めつけるものではありませんが、聴覚皮質が厚いほど読書が得意であることはわかっています。
では、聴覚皮質が厚ければ厚いほどいいのでしょうか?
たいていの人は左半球の聴覚皮質にはミエリン(髄鞘)がよりたくさんあります。
ミエリンは神経線維の伝達速度を高め、脳内の情報処理を迅速化する役割を持ちます。
このミエリンの影響で、左脳の皮質は薄くても広がりがあり、高速かつ正確な言語処理が可能になると考えられています。
一方で、情報を統合するような複雑なスキルには、より厚い皮質が有利とされます。
左側頭葉前部の厚みがその例で、この部分では、さまざまな情報を総合的に処理するために、神経細胞の重なりが多いと考えられています。
脳は「皮質可塑性」と呼ばれる柔軟性を持ち、新しいスキルを学んだり既存の能力を鍛えたりすることで変化します。
例えば、語学を集中的に学んだ若者は、言語に関わる脳の部位が厚くなることが分かっています。
同様に、読書も脳の構造を変え、特に左横側頭回や前側頭葉前部を強化する可能性があるわけです。
読書離れが進むことで、私たちの世界を理解する能力や、他者の心を読み解く力が失われていくかもしれません。
本を読む時間は単なる個人的な楽しみではなく、人間の知性や共感を育む大切な行為だと言えるでしょう。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院