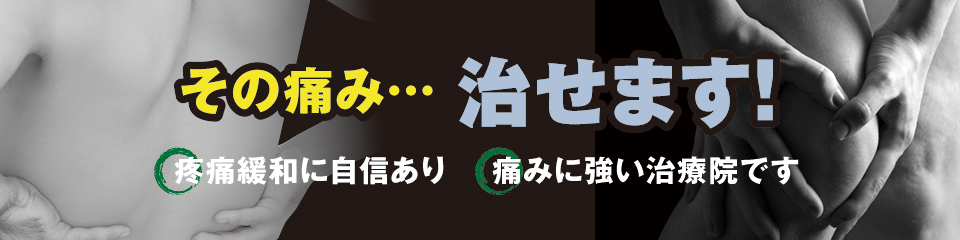2025年02月14日 [からだのこと]
ドアウェイ効果
お疲れ様です。院長です。
2月14日の金曜日でございます。
今日は「バレンタインデー」さらには、「チョコレートの日」でもあるそうです。
では元気にネタいきましょう。
物忘れが激しくなる年頃のわたくし院長ですが、今日はドアを通過しようとすると用事を忘れてしまう「ドアウェイ効果」ってもんのお話をしてみましょう。
ドアを開けて部屋をまたいだ瞬間、あるいはある場所から別の場所に移動した瞬間に記憶がすっとんでしまうことは、中高年の「あるある」なんです。
わたしは毎日のこれをやらかしているので心配でしたが、「ドアウェイ効果」という名称があるくらいですから、頻度の差はあれど経験者は多いでしょう。
例えば、リビングで「台所から何か取ってこよう」と思いつき、台所に着いた瞬間、その理由がすっかり頭から抜け落ちてしまう。
あるいは、買い物に行ったのに、店に入った途端に何を買おうとしていたかを忘れてしまうってヤツです。
これは単なる疲れや記憶力の低下だけが原因ではないそうなんです。
今回は「ドアウェイ効果」の背後にある科学的な理由に迫ってみましょう。
2011年、アメリカのノートルダム大学の研究チームは、「ドアウェイ効果」を検証する実験を行ないました。
この研究では、参加者に物を運ぶ仕事を与え、現実世界やバーチャル空間で部屋を移動するよう指示しました。
その結果、ドアを通過した後に、圧倒的に忘れ物が増えることが明らかになったそうです。
単に部屋を横切るだけの場合と比べても、ドアを通ることで記憶がリセットされる確率が高くなるそうです。
これは、私たちの脳が過去の出来事を整理して「区切り」をつける仕組みと関係しているという事らしいです。
この記憶の仕組みは「イベントホライズンモデル(Event Horizon Model:記憶や認知における境界)」によるもので、脳は出来事を連続的に記憶するのではなく、「その場所で起きたこと」を断片に分けて記憶する特徴があるそうなんです。
その結果、ドアを通ることで、「新しい場面が始まった」と脳が認識し、それまでの出来事と切り離してしまうんです。
ノートルダム大学心理学教授のガブリエル・ラドバンスキー氏は当時の声明で「別の部屋で下した決断や活動を思い出すのは、それが区分化されているため困難です。」と説明しました。
これが、前の部屋で考えていたことをすぐに思い出せなくなる理由なんだとか…。
そのためドアウェイ効果は位置更新効果とも呼ばれるそうです。
さらに2014年のイリノイ州ノックス大学研究では、実際にドアを通らなくても、この効果が起きることが報告されました。
つまり、脳は「ドアを通り抜ける場面」を想像するだけで、記憶を忘れやすくなることがわかったんだそうです。
これは、脳が場所の移動を想像しただけで、記憶の整理を始めてしまうためだと考えられています。
ただし、ドアウェイ効果がいつでも起こるわけではないこともわかっています。
2021年にオーストラリア、クイーンズランド大学が行ったVR(バーチャルリアリティ)を使った実験では、ドアウェイ効果がどのような条件で起こるのかが詳しく調べられました。
最初の実験では、参加者にVRヘッドセットを装着してもらい、仮想空間の中でテーブルに近づき、その上に置かれた物を覚えるという作業を行ないました。
そして、覚えた後で別のテーブルに移動し、そこで新たに物を覚えるよう指示されました。
ここで重要なのは、「次のテーブル」がどこに配置されていたかです。
同じ部屋の場合 : 次のテーブルが現在の部屋の中にあり、ドアを通る必要がない。
別の部屋の場合 : 次のテーブルが隣の部屋にあり、ドアを通過して移動する必要がある。
この実験では、ドアを通過した場合でも、記憶に特に影響がないことがわかりました。
つまり、「ドアを通過することだけでは、ドアウェイ効果は必ずしも発生しない」ということです。
クイーンズランド大学による次の実験では、「物を覚えながら同時に数を数える」という追加の作業を加えました。
すると結果が大きく変わりました。
この状況では、ドアウェイ効果が強く現れたんです。
研究者たちは、脳が同時に多くの情報を処理しようとすると負荷がかかり、記憶が曖昧になりやすいことを指摘しています。
また、仮想空間の部屋がほぼ同じ見た目だったことから、記憶の喪失は「ドアを通過する動作」そのものよりも「環境や状況の変化」による可能性が高いとも考えられるんだそうです。
「ドアウェイ効果」を理解することで、日常生活の困りごとを減らすヒントになるかもしれません。
例えば、移動してなにかを行う場合には、意識的に口に出して確認したり、メモを取るなどして「忘れにくい工夫」をするとか…。
また、何かを探しに行く時は、目的を心の中で繰り返しながら移動すると、記憶の断絶を防ぎやすいそうです。
まぁ、ある程度の年齢になるとこれは仕方ないものだと思ってましたが、まぁ脳の機能の一部なら余計に仕方ないですな。
ま、忘れれば思い出せばいいだけど、足掻いてもねぇ(笑)
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
2月14日の金曜日でございます。
今日は「バレンタインデー」さらには、「チョコレートの日」でもあるそうです。
では元気にネタいきましょう。
物忘れが激しくなる年頃のわたくし院長ですが、今日はドアを通過しようとすると用事を忘れてしまう「ドアウェイ効果」ってもんのお話をしてみましょう。
ドアを開けて部屋をまたいだ瞬間、あるいはある場所から別の場所に移動した瞬間に記憶がすっとんでしまうことは、中高年の「あるある」なんです。
わたしは毎日のこれをやらかしているので心配でしたが、「ドアウェイ効果」という名称があるくらいですから、頻度の差はあれど経験者は多いでしょう。
例えば、リビングで「台所から何か取ってこよう」と思いつき、台所に着いた瞬間、その理由がすっかり頭から抜け落ちてしまう。
あるいは、買い物に行ったのに、店に入った途端に何を買おうとしていたかを忘れてしまうってヤツです。
これは単なる疲れや記憶力の低下だけが原因ではないそうなんです。
今回は「ドアウェイ効果」の背後にある科学的な理由に迫ってみましょう。
2011年、アメリカのノートルダム大学の研究チームは、「ドアウェイ効果」を検証する実験を行ないました。
この研究では、参加者に物を運ぶ仕事を与え、現実世界やバーチャル空間で部屋を移動するよう指示しました。
その結果、ドアを通過した後に、圧倒的に忘れ物が増えることが明らかになったそうです。
単に部屋を横切るだけの場合と比べても、ドアを通ることで記憶がリセットされる確率が高くなるそうです。
これは、私たちの脳が過去の出来事を整理して「区切り」をつける仕組みと関係しているという事らしいです。
この記憶の仕組みは「イベントホライズンモデル(Event Horizon Model:記憶や認知における境界)」によるもので、脳は出来事を連続的に記憶するのではなく、「その場所で起きたこと」を断片に分けて記憶する特徴があるそうなんです。
その結果、ドアを通ることで、「新しい場面が始まった」と脳が認識し、それまでの出来事と切り離してしまうんです。
ノートルダム大学心理学教授のガブリエル・ラドバンスキー氏は当時の声明で「別の部屋で下した決断や活動を思い出すのは、それが区分化されているため困難です。」と説明しました。
これが、前の部屋で考えていたことをすぐに思い出せなくなる理由なんだとか…。
そのためドアウェイ効果は位置更新効果とも呼ばれるそうです。
さらに2014年のイリノイ州ノックス大学研究では、実際にドアを通らなくても、この効果が起きることが報告されました。
つまり、脳は「ドアを通り抜ける場面」を想像するだけで、記憶を忘れやすくなることがわかったんだそうです。
これは、脳が場所の移動を想像しただけで、記憶の整理を始めてしまうためだと考えられています。
ただし、ドアウェイ効果がいつでも起こるわけではないこともわかっています。
2021年にオーストラリア、クイーンズランド大学が行ったVR(バーチャルリアリティ)を使った実験では、ドアウェイ効果がどのような条件で起こるのかが詳しく調べられました。
最初の実験では、参加者にVRヘッドセットを装着してもらい、仮想空間の中でテーブルに近づき、その上に置かれた物を覚えるという作業を行ないました。
そして、覚えた後で別のテーブルに移動し、そこで新たに物を覚えるよう指示されました。
ここで重要なのは、「次のテーブル」がどこに配置されていたかです。
同じ部屋の場合 : 次のテーブルが現在の部屋の中にあり、ドアを通る必要がない。
別の部屋の場合 : 次のテーブルが隣の部屋にあり、ドアを通過して移動する必要がある。
この実験では、ドアを通過した場合でも、記憶に特に影響がないことがわかりました。
つまり、「ドアを通過することだけでは、ドアウェイ効果は必ずしも発生しない」ということです。
クイーンズランド大学による次の実験では、「物を覚えながら同時に数を数える」という追加の作業を加えました。
すると結果が大きく変わりました。
この状況では、ドアウェイ効果が強く現れたんです。
研究者たちは、脳が同時に多くの情報を処理しようとすると負荷がかかり、記憶が曖昧になりやすいことを指摘しています。
また、仮想空間の部屋がほぼ同じ見た目だったことから、記憶の喪失は「ドアを通過する動作」そのものよりも「環境や状況の変化」による可能性が高いとも考えられるんだそうです。
「ドアウェイ効果」を理解することで、日常生活の困りごとを減らすヒントになるかもしれません。
例えば、移動してなにかを行う場合には、意識的に口に出して確認したり、メモを取るなどして「忘れにくい工夫」をするとか…。
また、何かを探しに行く時は、目的を心の中で繰り返しながら移動すると、記憶の断絶を防ぎやすいそうです。
まぁ、ある程度の年齢になるとこれは仕方ないものだと思ってましたが、まぁ脳の機能の一部なら余計に仕方ないですな。
ま、忘れれば思い出せばいいだけど、足掻いてもねぇ(笑)
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院