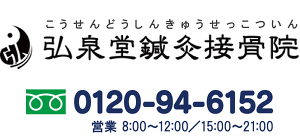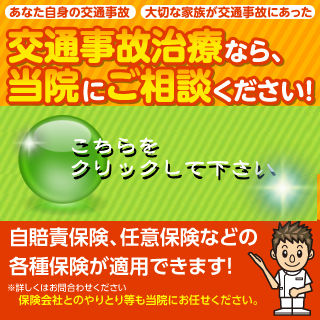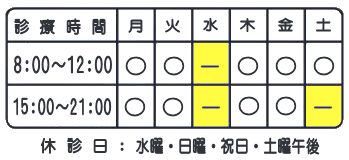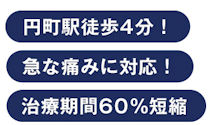クジラの唄
2025年04月09日 [動物のこと]
お疲れ様です。院長です。
4月9日の水曜日でございます。
何でも今日は「反核燃の日」なんだそうですよ。
では元気にネタいきましょう。
ザトウクジラのオスは、繁殖期に「歌」を歌うことで知られています。
さらに面白いことに、歌には流行があり、その年のヒットソングが東のクジラから西のクジラへと広がっていくことが、オーストラリア、クイーンズランド大学の研究で明らかになったそうです。
そして最新の研究によると、クジラの歌には、人間の言語と驚くほど似たパターンが隠されているそうです。
人間の言語には「ジップの法則」と呼ばれる特有のパターンがあるそうですが、クジラの歌もその法則が使用されていたそうなんです。
ではジップの法則とは何かを含め、詳しく見ていきましょう。
人間の言語には、どの国の言葉であろうとも、普遍的なパターンがあります。
この法則を、発見者である言語学者ジョージ・キングズリー・ジップにちなみ、「ジップの法則」というわけです。
これは、最も頻繁に使われる単語は、次に頻繁に使われる単語の2倍の頻度で現れ、3番目に多い単語の3倍の頻度で現れるという法則で、言語の効率的な伝達を支える重要な仕組みとなっているそうなんです。
簡単に言うと、よく使う言葉ほど短く、あまり使わない言葉は長くなるということのようです。
例えば、日本語の場合、「の」や「に」などの短い単語は頻繁に使われますが、「情報技術革命」、「大規模言語モデル」のような長い単語は短い単語よりあまり使われないと…。
この法則は、人間の話し言葉だけでなく、書き言葉や手話にも当てはまるんだそうです。
この法則は世界中のあらゆる言語で確認されていますが、これまで、動物のコミュニケーションに適用できる例は見つかっていませんでした。
今回、イスラエル、ヘブライ大学をはじめとする研究チームは、この人間の言語の普遍的パターンがクジラの歌にも当てはまるのかを確かめてみることにしました。
ですが、そもそも意味のわからないクジラの歌に含まれる単語の出現頻度を、どうやれば分析できるでしょう?
研究チームがヒントにしたのは、人間の赤ちゃんが言葉を学ぶ方法でした。
人間の赤ちゃんが、言葉を話せるようになるには単語を覚える必要があります。
そのためには単語の始まりと終わりの音を学び、各単語を区別できるようにならねばなりません。
だが話し言葉は連続的なもので、単語と単語の間にはっきりとした区切りがあるわけではありません。
ならば、赤ちゃんはどうやって単語と単語を聞き分けているのでしょう?
過去30年の研究で明らかになったことは、赤ちゃんはその文脈で意外に思える音に耳を澄ましているということでした。
じつは1つの単語を構成する音は比較的予測しやすいですが、単語と単語間の音は予測しにくく、赤ちゃんはこの予測しにくい音を手がかりに、単語の区切りを聞き分けているらしいんです。
今回研究チームは この赤ちゃんが音を聞き分ける方法を応用して、8年に渡って録音されたニューカレドニアに生息するザトウクジラの歌を分析しました。
その結果、クジラの歌もジップの法則に従っていることがわかったそうなんです。
人間の言語と同じく、クジラの歌でも、要素(音や単語など)から要素への移り変わりで予測しやすいものは、繰り返し現れる傾向にありました。
しかもその頻度はジップの法則(ジップ分布)が示す通りのものでした。
この発見から、とある興味深い疑問が浮かび上がってきます。
なぜクジラは人間と同じ法則を使用していたのでしょう?
進化の視点から言って、人間とクジラとはかなり離れた関係にあるはずです。
研究チームの仮説によれば、この奇妙な共通点は、人間とクジラが同じ方法で言語を学んでいることが関係していて、その方法とは「文化」なんだそうです。
文化を育む人間社会では、知識や技術などが次の世代に受け継がれ、だんだんと改善されていきます。
ですから、学習しにくいやり方はいずれ廃れ、学習しやすい方法が生き残ります。
実際に、私たち人間は、統計学的にわかりやすく、かつジップの法則に従ったものだと学習しやすいことが証明されているといいます。
それはクジラにとってもそうなのかもしれません。
人間とクジラは文化を継承するうちに、この簡単な学習法を育んでその結果、両者の言葉と歌には共通点ができたと考えられるそうです。
クジラの歌が人間の言語と似た構造を持っていることがわかりましたが、それは「クジラと会話できる」という意味ではもちろんありません。
今回の研究では、クジラの歌の「意味」についてはまったく分析していませんし、そもそも、クジラの歌が意味を持つものなのか、それとも楽器の演奏のように単なるリズムやメロディなのかも不明だそうです。
まぁ、クジラも高度な知能を持ってそうですし、何らかの言語に近いコミュニケーションツールはあると思いますけど、それが解析できるかどうかはまた別の問題ですよね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
4月9日の水曜日でございます。
何でも今日は「反核燃の日」なんだそうですよ。
では元気にネタいきましょう。
ザトウクジラのオスは、繁殖期に「歌」を歌うことで知られています。
さらに面白いことに、歌には流行があり、その年のヒットソングが東のクジラから西のクジラへと広がっていくことが、オーストラリア、クイーンズランド大学の研究で明らかになったそうです。
そして最新の研究によると、クジラの歌には、人間の言語と驚くほど似たパターンが隠されているそうです。
人間の言語には「ジップの法則」と呼ばれる特有のパターンがあるそうですが、クジラの歌もその法則が使用されていたそうなんです。
ではジップの法則とは何かを含め、詳しく見ていきましょう。
人間の言語には、どの国の言葉であろうとも、普遍的なパターンがあります。
この法則を、発見者である言語学者ジョージ・キングズリー・ジップにちなみ、「ジップの法則」というわけです。
これは、最も頻繁に使われる単語は、次に頻繁に使われる単語の2倍の頻度で現れ、3番目に多い単語の3倍の頻度で現れるという法則で、言語の効率的な伝達を支える重要な仕組みとなっているそうなんです。
簡単に言うと、よく使う言葉ほど短く、あまり使わない言葉は長くなるということのようです。
例えば、日本語の場合、「の」や「に」などの短い単語は頻繁に使われますが、「情報技術革命」、「大規模言語モデル」のような長い単語は短い単語よりあまり使われないと…。
この法則は、人間の話し言葉だけでなく、書き言葉や手話にも当てはまるんだそうです。
この法則は世界中のあらゆる言語で確認されていますが、これまで、動物のコミュニケーションに適用できる例は見つかっていませんでした。
今回、イスラエル、ヘブライ大学をはじめとする研究チームは、この人間の言語の普遍的パターンがクジラの歌にも当てはまるのかを確かめてみることにしました。
ですが、そもそも意味のわからないクジラの歌に含まれる単語の出現頻度を、どうやれば分析できるでしょう?
研究チームがヒントにしたのは、人間の赤ちゃんが言葉を学ぶ方法でした。
人間の赤ちゃんが、言葉を話せるようになるには単語を覚える必要があります。
そのためには単語の始まりと終わりの音を学び、各単語を区別できるようにならねばなりません。
だが話し言葉は連続的なもので、単語と単語の間にはっきりとした区切りがあるわけではありません。
ならば、赤ちゃんはどうやって単語と単語を聞き分けているのでしょう?
過去30年の研究で明らかになったことは、赤ちゃんはその文脈で意外に思える音に耳を澄ましているということでした。
じつは1つの単語を構成する音は比較的予測しやすいですが、単語と単語間の音は予測しにくく、赤ちゃんはこの予測しにくい音を手がかりに、単語の区切りを聞き分けているらしいんです。
今回研究チームは この赤ちゃんが音を聞き分ける方法を応用して、8年に渡って録音されたニューカレドニアに生息するザトウクジラの歌を分析しました。
その結果、クジラの歌もジップの法則に従っていることがわかったそうなんです。
人間の言語と同じく、クジラの歌でも、要素(音や単語など)から要素への移り変わりで予測しやすいものは、繰り返し現れる傾向にありました。
しかもその頻度はジップの法則(ジップ分布)が示す通りのものでした。
この発見から、とある興味深い疑問が浮かび上がってきます。
なぜクジラは人間と同じ法則を使用していたのでしょう?
進化の視点から言って、人間とクジラとはかなり離れた関係にあるはずです。
研究チームの仮説によれば、この奇妙な共通点は、人間とクジラが同じ方法で言語を学んでいることが関係していて、その方法とは「文化」なんだそうです。
文化を育む人間社会では、知識や技術などが次の世代に受け継がれ、だんだんと改善されていきます。
ですから、学習しにくいやり方はいずれ廃れ、学習しやすい方法が生き残ります。
実際に、私たち人間は、統計学的にわかりやすく、かつジップの法則に従ったものだと学習しやすいことが証明されているといいます。
それはクジラにとってもそうなのかもしれません。
人間とクジラは文化を継承するうちに、この簡単な学習法を育んでその結果、両者の言葉と歌には共通点ができたと考えられるそうです。
クジラの歌が人間の言語と似た構造を持っていることがわかりましたが、それは「クジラと会話できる」という意味ではもちろんありません。
今回の研究では、クジラの歌の「意味」についてはまったく分析していませんし、そもそも、クジラの歌が意味を持つものなのか、それとも楽器の演奏のように単なるリズムやメロディなのかも不明だそうです。
まぁ、クジラも高度な知能を持ってそうですし、何らかの言語に近いコミュニケーションツールはあると思いますけど、それが解析できるかどうかはまた別の問題ですよね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院