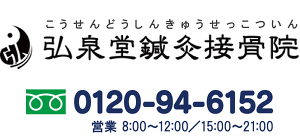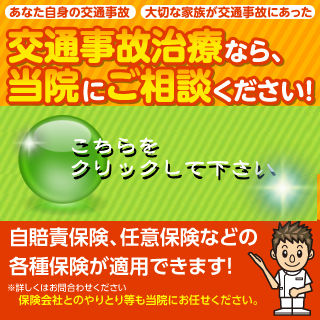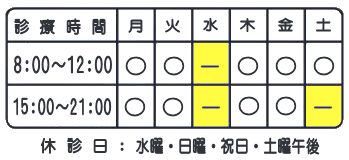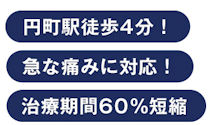適応進化
2025年02月25日 [動物のこと]
お疲れ様です。院長です。
2月25日の火曜日でございます。
何でも今日は「夕刊紙の日」なんだそうです。
では元気にネタいきましょう。
今日のネタは人間の影響で、適応・進化している6種の動植物についてお話しします。
彼らは変わりゆく環境の適応し、生き残るために様々な変化、進化を続けています。
ですが最近の変化は、どうやら人間の影響が大きいようです。
産業革命の時代、煤(スス)で環境が汚染されたために、そこに生息する蛾が白から真っ黒に変化したことが知られています。
煤でおおわれた樹木では、白よりも黒い方が生き残りやすかったからです。
人間の影響による変化への適応は、世界のそこかしこで起きています。
人間中心の世界で生き抜くために進化した6種の動植物を見ていきましょう。
米国ネブラスカ州南西部に生息するサンショクツバメは、橋の下に巣を作る習性があり、そのせいで車との交通事故が頻発していました。
ところが2013年の研究では、この状況への適応進化としてツバメの翼が短くなっていることが明らかになっています。
短い翼は長いものに比べて小回りがきき、猛スピードで走っている車を避けやすいと…。
この発見をした鳥類学者によれば、その違いは「U-2偵察機と戦闘機のようなもの」であるそうです。
丈夫で腐りにくく、赤みがかった色合いが美しいマホガニー(桃花心木)は、高級木材の代名詞です。
そのおかげで伐採が進み、1970年以降、国によっては70%以上も減少し、大木はほとんど姿を消しました。
決して絶滅したわけではなく、今でもさまざまな地域で見ることができますが、その姿は昔とは違います。
かつてマホガニーは高さ20mを超えることもある巨木でした。
ところが、現代のマホガニーはずっと小さいんです。
大きな個体が伐採されてしまったため、その背の高さを支えていた遺伝子を残せなかったことが原因だと考えられているそうです。
カリブ海の海底300mで2018年に発見された新種のクモヒトデ「Astrophiura caroleae」は、意外な場所が大好きです。
生きている個体は、おそらく漁師が海に投げ捨てたと思われるビール瓶のうえでしか発見されたことがないんだそうです。
唯一の例外は、ゴムのタイヤです。
このクモヒトデは、岩のような硬い場所を好むと考えられています。
ですから人間によって捨てられたゴミのうえでもかなり快適に過ごせるらしいです。
もともとカササギは、巣を棘のある枝などでおおって、カラスのような卵を狙う外敵から子供たちを守る習性で知られていました。
ところが最近のカササギの中に、棘枝の代わりに、鳥除けスパイクを利用するものが現れたそうなんです。
これはほんの一例で、最近の鳥たちは巣に人工素材を当たり前のように使っているそうです。
鳥を除けるために設置したスパイクが逆に有効活用されるとは皮肉なもんですなぁ。
オランダで行われた調査によると、都市部に生息するモリマイマイ(grove snail)というカタツムリの殻が薄くなっていることが判明しました。
これは暑さ対策だと考えられています。
都市部は田舎より最大8度も気温が高い。
殻の色が濃いままだと熱を吸収しやすく、暑さで死んでしまう恐れがあるため、色を薄くすることで、暑い環境でも生きられるよう進化したようです。
モザンビーク内戦中、密猟が原因で、ゴロンゴサ国立公園のアフリカゾウは個体数が1割にまで激減しました。
現在、その数は元に戻り、動物の個体数回復の重要な成功事例となっていますが、乱獲の爪痕は残されています。
牙のないメスの象が増えているそうなんです。
これは牙がない方が密猟者に狙われにくいためだと考えられています。
こうした変化はタンザニアでも確認されているそうです。
こういった環境に適応した進化は人間にも現在進行形で起きています。
標高3500mを超えるチベット高原で暮らす女性たちを対象にした2022年の研究では、1つのヘモグロビンが運べる酸素の量が多いことが明らかになったそうです。
これは、酸素の薄い高地で暮らすために適応していったものと考えられています。
また、子供をたくさん産んだ女性は、肺への血の流れがよく、心臓の左心室(酸素を運ぶ血液を体に送り出す部屋)が平均よりも広いことが判明しています。
これは、これは現在進行形の自然選択の一例と言えるかもしれません。
まぁ、人間の影響もある意味生存の中の話ですから、仕方ない部分もあると思いますが、人間も進化してるってのは驚きですね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
2月25日の火曜日でございます。
何でも今日は「夕刊紙の日」なんだそうです。
では元気にネタいきましょう。
今日のネタは人間の影響で、適応・進化している6種の動植物についてお話しします。
彼らは変わりゆく環境の適応し、生き残るために様々な変化、進化を続けています。
ですが最近の変化は、どうやら人間の影響が大きいようです。
産業革命の時代、煤(スス)で環境が汚染されたために、そこに生息する蛾が白から真っ黒に変化したことが知られています。
煤でおおわれた樹木では、白よりも黒い方が生き残りやすかったからです。
人間の影響による変化への適応は、世界のそこかしこで起きています。
人間中心の世界で生き抜くために進化した6種の動植物を見ていきましょう。
米国ネブラスカ州南西部に生息するサンショクツバメは、橋の下に巣を作る習性があり、そのせいで車との交通事故が頻発していました。
ところが2013年の研究では、この状況への適応進化としてツバメの翼が短くなっていることが明らかになっています。
短い翼は長いものに比べて小回りがきき、猛スピードで走っている車を避けやすいと…。
この発見をした鳥類学者によれば、その違いは「U-2偵察機と戦闘機のようなもの」であるそうです。
丈夫で腐りにくく、赤みがかった色合いが美しいマホガニー(桃花心木)は、高級木材の代名詞です。
そのおかげで伐採が進み、1970年以降、国によっては70%以上も減少し、大木はほとんど姿を消しました。
決して絶滅したわけではなく、今でもさまざまな地域で見ることができますが、その姿は昔とは違います。
かつてマホガニーは高さ20mを超えることもある巨木でした。
ところが、現代のマホガニーはずっと小さいんです。
大きな個体が伐採されてしまったため、その背の高さを支えていた遺伝子を残せなかったことが原因だと考えられているそうです。
カリブ海の海底300mで2018年に発見された新種のクモヒトデ「Astrophiura caroleae」は、意外な場所が大好きです。
生きている個体は、おそらく漁師が海に投げ捨てたと思われるビール瓶のうえでしか発見されたことがないんだそうです。
唯一の例外は、ゴムのタイヤです。
このクモヒトデは、岩のような硬い場所を好むと考えられています。
ですから人間によって捨てられたゴミのうえでもかなり快適に過ごせるらしいです。
もともとカササギは、巣を棘のある枝などでおおって、カラスのような卵を狙う外敵から子供たちを守る習性で知られていました。
ところが最近のカササギの中に、棘枝の代わりに、鳥除けスパイクを利用するものが現れたそうなんです。
これはほんの一例で、最近の鳥たちは巣に人工素材を当たり前のように使っているそうです。
鳥を除けるために設置したスパイクが逆に有効活用されるとは皮肉なもんですなぁ。
オランダで行われた調査によると、都市部に生息するモリマイマイ(grove snail)というカタツムリの殻が薄くなっていることが判明しました。
これは暑さ対策だと考えられています。
都市部は田舎より最大8度も気温が高い。
殻の色が濃いままだと熱を吸収しやすく、暑さで死んでしまう恐れがあるため、色を薄くすることで、暑い環境でも生きられるよう進化したようです。
モザンビーク内戦中、密猟が原因で、ゴロンゴサ国立公園のアフリカゾウは個体数が1割にまで激減しました。
現在、その数は元に戻り、動物の個体数回復の重要な成功事例となっていますが、乱獲の爪痕は残されています。
牙のないメスの象が増えているそうなんです。
これは牙がない方が密猟者に狙われにくいためだと考えられています。
こうした変化はタンザニアでも確認されているそうです。
こういった環境に適応した進化は人間にも現在進行形で起きています。
標高3500mを超えるチベット高原で暮らす女性たちを対象にした2022年の研究では、1つのヘモグロビンが運べる酸素の量が多いことが明らかになったそうです。
これは、酸素の薄い高地で暮らすために適応していったものと考えられています。
また、子供をたくさん産んだ女性は、肺への血の流れがよく、心臓の左心室(酸素を運ぶ血液を体に送り出す部屋)が平均よりも広いことが判明しています。
これは、これは現在進行形の自然選択の一例と言えるかもしれません。
まぁ、人間の影響もある意味生存の中の話ですから、仕方ない部分もあると思いますが、人間も進化してるってのは驚きですね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院