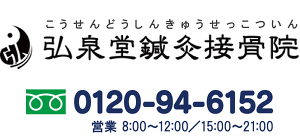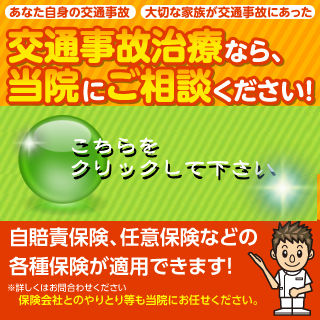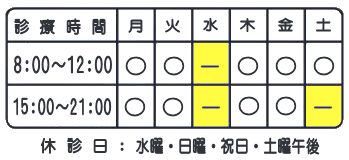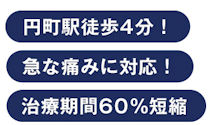外耳と魚
2025年02月21日 [からだのこと]
お疲れ様です。院長です。
2月21日の金曜日でございます。
なんでも今日は「国際母語デー」なんだそうです。
では元気にネタいきましょう。
人間の中耳は、魚のエラを起源に持つことが2022年の化石の研究で明らかとなりましたが、今回の研究テーマは外耳です。
外耳とは、耳の外側にある部分で、音を集めて耳の中に伝える役割を持つ構造を持つ器官です。
米国の研究チームによる新たな遺伝子編集を使った実験では、古代魚のエラに存在する軟骨が、数百万年前の進化を経て、私たち哺乳類の外耳に変化したことが示されています。
中耳のみならず外耳も魚由来だったようなんです。
それどころか、私たちの耳の起源は、”生きている化石”と呼ばれるカブトガニにまで遡れるかもしれないという話です。
2022年の研究によって、「中耳」(鼓膜の向こう側の部分。空気が入った空間と3つの小骨で構成される)が古代魚のエラに起源をもつことが明らかにされていました。
この進化の事例は、生命が1つの構造を変化させ、また別の用途に利用してきただろうことを示ししています。
ならば、中耳だけでなく、外耳もまた古代魚の体を再利用したものかもしれません。
米国南カリフォルニア大学のゲイジ・クランプ教授は、「当初、外耳の進化的起源は完全なブラックボックスでした」と、ニュースリリースで述べています。
人間などの哺乳類の「外耳」(外から見える耳と、そこから鼓膜までの部分)の軟骨は、「弾性軟骨」とよばれ、ユニークな特徴があります。
人間の鼻にある硝子軟骨や、腰の椎間板にある線維軟骨に比べると、ずっと柔軟なんです。
そもそも、この弾性軟骨が哺乳類以外の動物にもあるのかどうか、詳しいことは不明でした。
そこでクランプ教授らは、タンパク質染色を用いてゼブラフィッシュやタイセイヨウサケなどを調べてみました。
すると、確かに弾性軟骨は、魚のエラにもあることがわかりました。
これらの魚はどれも硬骨魚類であり、このグループでは弾性軟骨が一般的だろうことを告げるものでした。
次に、発見された魚のエラの弾性軟骨と哺乳類の外耳との間に、本当に進化的なつながりがあるのかどうかが検証されました。
弾性軟骨はすぐに分解されてしまうため、なかなか化石として残ってくれません。
そこで魚と哺乳類の遺伝子の中に、エラと外耳のつながりを示す手がかりがないか探されました。
その手がかりとは、「エンハンサー」と呼ばれる短いDNA配列のことでした。
これは遺伝子の働きを強めるスイッチのようなもので、特定の組織でしか機能しないものです。
もし人間の外耳のエンハンサーが魚のエラで機能するなら、外耳とエラには関連があるということになります。
そして確かに、人間の外耳エンハンサーは、ゼブラフィッシュのエラで見事にスイッチが入ったそうなんです。
さらにクランプ教授らはその逆の流れも確認しています。
ゼブラフィッシュのエラ・エンハンサーをマウスの遺伝子に挿入してみたところ、こちらでもエラ・エンハンサーがマウスの外耳で活性化することがわかりました。
こうした結果は、魚のエラと哺乳類の外耳には遺伝的な関連があることを物語るものです。
その後の実験では、オタマジャクシやトカゲでも同様のことを行い、両生類や爬虫類も魚からエラと耳の構造を受け継いでいることが確かめられました。
トカゲの場合、外耳道でエンハンサーのスイッチが入ったため、爬虫類が地上に登場した頃(約3億1500万年前)には、弾性軟骨がエラから外耳へと変化し出していたことがうかがえます。
なんと、こうした弾性軟骨のエンハンサーは、カブトガニにまでたどられているそうです。
4億年前に出現したカブトガニは、「生きた化石」と言われるほど古い種です。
このことは、人間の外耳が想像以上に古い起源を持つ可能性を示しています。
研究チームによれば、魚のエラを作り出す遺伝的なプログラムは、脊椎動物の進化過程で何度も再利用され、さまざまなエラや耳の構造を作り出してきたと考えられるそうです。
魚のエラ由来とはねぇ…。
想像も出来ませんね(笑)
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨
2月21日の金曜日でございます。
なんでも今日は「国際母語デー」なんだそうです。
では元気にネタいきましょう。
人間の中耳は、魚のエラを起源に持つことが2022年の化石の研究で明らかとなりましたが、今回の研究テーマは外耳です。
外耳とは、耳の外側にある部分で、音を集めて耳の中に伝える役割を持つ構造を持つ器官です。
米国の研究チームによる新たな遺伝子編集を使った実験では、古代魚のエラに存在する軟骨が、数百万年前の進化を経て、私たち哺乳類の外耳に変化したことが示されています。
中耳のみならず外耳も魚由来だったようなんです。
それどころか、私たちの耳の起源は、”生きている化石”と呼ばれるカブトガニにまで遡れるかもしれないという話です。
2022年の研究によって、「中耳」(鼓膜の向こう側の部分。空気が入った空間と3つの小骨で構成される)が古代魚のエラに起源をもつことが明らかにされていました。
この進化の事例は、生命が1つの構造を変化させ、また別の用途に利用してきただろうことを示ししています。
ならば、中耳だけでなく、外耳もまた古代魚の体を再利用したものかもしれません。
米国南カリフォルニア大学のゲイジ・クランプ教授は、「当初、外耳の進化的起源は完全なブラックボックスでした」と、ニュースリリースで述べています。
人間などの哺乳類の「外耳」(外から見える耳と、そこから鼓膜までの部分)の軟骨は、「弾性軟骨」とよばれ、ユニークな特徴があります。
人間の鼻にある硝子軟骨や、腰の椎間板にある線維軟骨に比べると、ずっと柔軟なんです。
そもそも、この弾性軟骨が哺乳類以外の動物にもあるのかどうか、詳しいことは不明でした。
そこでクランプ教授らは、タンパク質染色を用いてゼブラフィッシュやタイセイヨウサケなどを調べてみました。
すると、確かに弾性軟骨は、魚のエラにもあることがわかりました。
これらの魚はどれも硬骨魚類であり、このグループでは弾性軟骨が一般的だろうことを告げるものでした。
次に、発見された魚のエラの弾性軟骨と哺乳類の外耳との間に、本当に進化的なつながりがあるのかどうかが検証されました。
弾性軟骨はすぐに分解されてしまうため、なかなか化石として残ってくれません。
そこで魚と哺乳類の遺伝子の中に、エラと外耳のつながりを示す手がかりがないか探されました。
その手がかりとは、「エンハンサー」と呼ばれる短いDNA配列のことでした。
これは遺伝子の働きを強めるスイッチのようなもので、特定の組織でしか機能しないものです。
もし人間の外耳のエンハンサーが魚のエラで機能するなら、外耳とエラには関連があるということになります。
そして確かに、人間の外耳エンハンサーは、ゼブラフィッシュのエラで見事にスイッチが入ったそうなんです。
さらにクランプ教授らはその逆の流れも確認しています。
ゼブラフィッシュのエラ・エンハンサーをマウスの遺伝子に挿入してみたところ、こちらでもエラ・エンハンサーがマウスの外耳で活性化することがわかりました。
こうした結果は、魚のエラと哺乳類の外耳には遺伝的な関連があることを物語るものです。
その後の実験では、オタマジャクシやトカゲでも同様のことを行い、両生類や爬虫類も魚からエラと耳の構造を受け継いでいることが確かめられました。
トカゲの場合、外耳道でエンハンサーのスイッチが入ったため、爬虫類が地上に登場した頃(約3億1500万年前)には、弾性軟骨がエラから外耳へと変化し出していたことがうかがえます。
なんと、こうした弾性軟骨のエンハンサーは、カブトガニにまでたどられているそうです。
4億年前に出現したカブトガニは、「生きた化石」と言われるほど古い種です。
このことは、人間の外耳が想像以上に古い起源を持つ可能性を示しています。
研究チームによれば、魚のエラを作り出す遺伝的なプログラムは、脊椎動物の進化過程で何度も再利用され、さまざまなエラや耳の構造を作り出してきたと考えられるそうです。
魚のエラ由来とはねぇ…。
想像も出来ませんね(笑)
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨