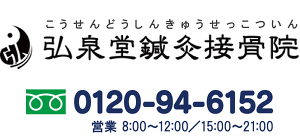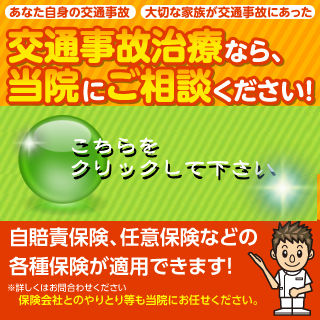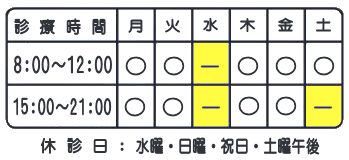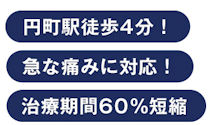思考力低下
2025年02月17日 [からだのこと]
お疲れ様です。院長です。
2月17日の月曜
なんでも今日は「中部国際空港開港記念日」なんだそうですよ。
では元気にネタいきましょう。
AIがあなたの考える力を奪う?
「便利すぎる時代」の危険性とは…。
「スマホやパソコン、そしてAIがあれば、なんでもすぐに答えがわかる。」便利な時代に生きる私たちは、頭を使う機会を失っているかもしれません。
最近の研究では、AIツールの使いすぎが「考える力」に悪影響を与える可能性があることが明らかになりました。
特に若い世代でこの傾向が強いという話です。
スイスの研究者マイケル・ガーリッヒ氏が行った調査によると、AIツールを多用する人ほど「自分で深く考える力」が低下する可能性があるそうです。
例えば、昔は電話番号を覚えるのが当たり前でしたけど、今はスマホが全部記録していますから、自分で覚える必要がほとんどなくなってます。
同じように、学校の宿題をAIに頼ると、答えはすぐに手に入ってしまいます。
つまり、それを自分で考えたり、記憶したり、調べたりする機会は失われてしまうわけです。
AIに頼りすぎると、「頭を使わずに済ませる」という習慣ができてしまいます。
つまり、自分で物事を判断したり、深く考えたりする力がどんどん弱くなる可能性があるわけなんです。
この研究では、666人を対象にアンケートとインタビューを実施しました。
その結果、若い世代ほどAIを頻繁に使い、その分「考える力」が低い傾向が明らかになったそうなんです。
一方で、年配の世代(46歳以上)はAIの利用が少なく、逆に考える力が高いという結果でした。
そりゃ、AIを使いこなせないっ絵だけの話なんですけどね(笑)
また、大学教育を受けた人はAIの利用にかかわらず考える力が高いこともわかったそうです。
つまり、教育の質や学ぶ姿勢が、AIの影響を和らげる可能性があるという話です。
だからといって、AIを利用するのが悪いということでは決してありません。
便利に使えば、時間を節約したり、新しいことを学んだりする助けになります。
ガーリッヒ氏は「AIツールは便利だが、その使い方を間違えると、考える力を奪われてしまう可能性がある、しかし、正しい使い方を学べばこの問題を克服できる」とも述べています。
AIはあくまでも「手助けしてくれるアシスタント」です。
AIを使う時には、まずは自分で考え、AIの出した答えをそのまま受け入れるのではなく、「これは本当に正しいのか?」と疑問を持ち、何度も調べ直すことが大切だということです。
ChatGPTやジェミニのような、生成系Aは、インターネットから収集された膨大なデータで学習された「大規模言語モデル(LLM)」です。
そのため、収集されたデータが偏っている場合には、間違った答えを導き出すこともあります。
自信満々にしれっと嘘をつくこともあるわけです。
これはハルシネーション(幻覚)と呼ばれており、AIが常に正しいとも限らない。
また、聞き方(プロンプト)次第で回答にぶれが生じたり、聞くたびに違った答えが出ることもあります。
フランスの哲学者・パスカルは「人間は考える葦(あし)である」という有名な言葉を残しました。
「人間は自然界の中において、葦(水辺に生える弱く細い多年草)のように弱い存在だが、人間は頭を使って考えることができる。考える事こそ人間に与えられた偉大な力である」と言う意味です。
考える力が奪われてしまったら人間は本当の葦になってしまします。
そうならないよう全部AIに任せっきりにせず、自分で考える時間や覚える時間を確保しましよう。
もう軽いボケ防止ですな(笑)
逆に我々中高年は、こういった最先端ツールを使えるように努力することで、ボケ防止になりますから逆の発想ですね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨
2月17日の月曜
なんでも今日は「中部国際空港開港記念日」なんだそうですよ。
では元気にネタいきましょう。
AIがあなたの考える力を奪う?
「便利すぎる時代」の危険性とは…。
「スマホやパソコン、そしてAIがあれば、なんでもすぐに答えがわかる。」便利な時代に生きる私たちは、頭を使う機会を失っているかもしれません。
最近の研究では、AIツールの使いすぎが「考える力」に悪影響を与える可能性があることが明らかになりました。
特に若い世代でこの傾向が強いという話です。
スイスの研究者マイケル・ガーリッヒ氏が行った調査によると、AIツールを多用する人ほど「自分で深く考える力」が低下する可能性があるそうです。
例えば、昔は電話番号を覚えるのが当たり前でしたけど、今はスマホが全部記録していますから、自分で覚える必要がほとんどなくなってます。
同じように、学校の宿題をAIに頼ると、答えはすぐに手に入ってしまいます。
つまり、それを自分で考えたり、記憶したり、調べたりする機会は失われてしまうわけです。
AIに頼りすぎると、「頭を使わずに済ませる」という習慣ができてしまいます。
つまり、自分で物事を判断したり、深く考えたりする力がどんどん弱くなる可能性があるわけなんです。
この研究では、666人を対象にアンケートとインタビューを実施しました。
その結果、若い世代ほどAIを頻繁に使い、その分「考える力」が低い傾向が明らかになったそうなんです。
一方で、年配の世代(46歳以上)はAIの利用が少なく、逆に考える力が高いという結果でした。
そりゃ、AIを使いこなせないっ絵だけの話なんですけどね(笑)
また、大学教育を受けた人はAIの利用にかかわらず考える力が高いこともわかったそうです。
つまり、教育の質や学ぶ姿勢が、AIの影響を和らげる可能性があるという話です。
だからといって、AIを利用するのが悪いということでは決してありません。
便利に使えば、時間を節約したり、新しいことを学んだりする助けになります。
ガーリッヒ氏は「AIツールは便利だが、その使い方を間違えると、考える力を奪われてしまう可能性がある、しかし、正しい使い方を学べばこの問題を克服できる」とも述べています。
AIはあくまでも「手助けしてくれるアシスタント」です。
AIを使う時には、まずは自分で考え、AIの出した答えをそのまま受け入れるのではなく、「これは本当に正しいのか?」と疑問を持ち、何度も調べ直すことが大切だということです。
ChatGPTやジェミニのような、生成系Aは、インターネットから収集された膨大なデータで学習された「大規模言語モデル(LLM)」です。
そのため、収集されたデータが偏っている場合には、間違った答えを導き出すこともあります。
自信満々にしれっと嘘をつくこともあるわけです。
これはハルシネーション(幻覚)と呼ばれており、AIが常に正しいとも限らない。
また、聞き方(プロンプト)次第で回答にぶれが生じたり、聞くたびに違った答えが出ることもあります。
フランスの哲学者・パスカルは「人間は考える葦(あし)である」という有名な言葉を残しました。
「人間は自然界の中において、葦(水辺に生える弱く細い多年草)のように弱い存在だが、人間は頭を使って考えることができる。考える事こそ人間に与えられた偉大な力である」と言う意味です。
考える力が奪われてしまったら人間は本当の葦になってしまします。
そうならないよう全部AIに任せっきりにせず、自分で考える時間や覚える時間を確保しましよう。
もう軽いボケ防止ですな(笑)
逆に我々中高年は、こういった最先端ツールを使えるように努力することで、ボケ防止になりますから逆の発想ですね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨