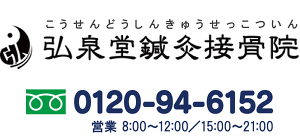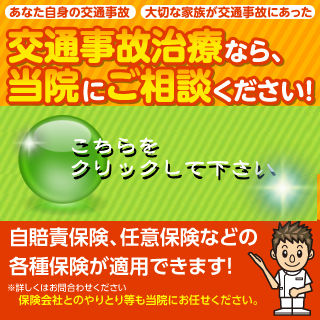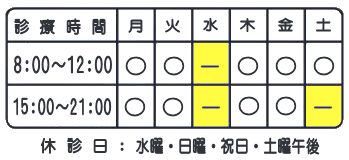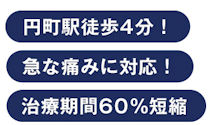忘却の彼方
2025年01月24日 [からだのこと]
お疲れ様です。院長です。
1月24日の金曜日でございます。
最近、歳のせいか物忘れが激しすぎます。
買い物しようと町まで出かけたら、財布を忘れて、愉快なサザエさん現象をリアルで体験してしまったり、用事があって席を立ったはずなのに、何をしようとしていたのか忘れちゃうとかの現象が日常的に起こるようになってきました。
そんな物忘れは、多くの場合、ネガティブにとらえられがちですが、実は人間は、物忘れをするように進化をしてきたのだという説があります。
四六時中物忘れをするのはまた別の問題ですが、物忘れは、人間が生き延びるための生存戦略の1つなのだという話です。
では、いったいどんなメリットがあるのでしょう?
詳しく見ていきましょう。
トリニティ・カレッジ・ダブリンの神経科学者スヴェン・ヴァンネステ氏とエルヴァ・アルルチェルヴァン氏は、The Conversationで、忘れることの利点について説明してくれています。
19世紀のドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスは、人が物事を忘れる理由は、ただ単に記憶が薄れていくことが原因だと考えました。
彼が考案した「忘却曲線」によると、私たちが何かを新しく覚えたとき、その細かい部分はあっという間に忘れてしまいますが、その忘却速度は時間とともに緩やかになっていくという話です。
これは忘却についての初期の研究成果で、最近では神経科学的に再現されています。
ですが忘却は、ただの時間による記憶の風化というだけでなく、機能的な役割があると考えられています。
と言うのも、私たちの身の回りには洪水のように情報があふれているからです。
もしも、そのすべてを記憶しようとすれば、本当に大切な情報を記憶しておくことが難しくなるでしょう。
それを防ぐ方法の1つは、無視することです。
ノーベル賞受賞神経学者エリック・カンデル氏などによる研究では、記憶の形成を支えているのは、脳内の神経細胞同士のつながり(シナプス)の強まりであることを明らかにしています。
何かに注意を払うことは、シナプス結合を強化し、その記憶をより濃いものにすることにほかなりません。
ですから、それとは逆に注意を向けないことで、身の回りに溢れているどうでもいい情報を忘れることができるわけです。
新しい情報に対処するために、それまでの記憶が書き換えられ、それが忘却につながることもあります。
例えば、日々の通勤・通学では、いつもの道順をたどるでしょう。
するとその都度、脳の結合が強化され、その道順がしっかりと記憶されていくわけです。
ところが、ある日、道路の1つが通行止めになり、しばらく別の道を迂回せねばならなくなったとします。
この場合、新しい状況に対応するために、記憶を柔軟に修正してやる必要があるわけです。
そのためには一部の記憶結合を弱めて、新たな結合を強化します。
こうすることで新しい道順を記憶するわけなんです。
こうした記憶の更新ができなければ、困ったことになります。
例えば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、恐ろしい記憶を更新できず、それによっていつまでも苦しめられる症状です。
こうした記憶の柔軟さは、私たちの祖先の命を救ってきました。
例えば、狩猟採集生活を送っていた私たち祖先が、安全な水場を発見し、日々そこを訪れていたとしましょう。
ある日、そこで敵対する集落や危険な野生動物を発見しました。
この場合、彼らの脳は、水場がもう安全ではないと記憶を更新する必要があるわけです。
そうすることで、命を落としかねない危険から身を守ることができます。
じつは忘却の中には、単純に記憶が失われたことが原因でないケースもあります。
記憶自体はあるのに、そこにアクセスできなくて思い出せなくなっている場合があります。
たとえば、マウスによる実験では、忘れられたはずの記憶がシナプス結合を助けてやることで思い出されることが確認されています。
またアクセスできなくて思い出せないという経験は意外と身近なもので、何かの名前が喉元まで出かかっているというのに、思い出せないという経験は誰にもあるでしょう。
この現象は「舌先現象」とも呼ばれています。
1960年代にこれを研究した心理学者ロジャー・ブラウンとデビッド・マクニールは、名前を思い出せない人が、その名前の要素(たとえばSで始まる、短いなど)を特定できることに気がつきました。
これは情報が完全には忘れられていないことを告げているわけです。
舌先現象についての仮説によれば、思い出せないのは、名前とその意味を結びつける記憶結合が弱まったからであるという話です。
ですが別の可能性として、情報はきちんとあるのに、ただアクセスできないだけであることを伝えるサインとして機能しているとも考えられるそうなんです。
そう考えると、年齢を重ねて知識が増えた人ほど、舌先現象を経験しやすくなる理由をうまく説明できますね。
脳にたくさん情報がある人は、それらを整理して特定の情報を思い出すことが大変になります。
そこで脳が舌先現象を経験させて、「情報自体は消えていない、頑張れば思い出せるぞ」と告げているかもしれないんだそうです。
要するに、私たちが物事を忘れるのは、理由あってのことなのです。
情報を無視したり、時間とともに記憶が薄れたり、ときには記憶を更新するために、古い物事を忘れるかもしれません。
あるいは忘れたと思っていた記憶が、じつは忘れてはおらず、単にアクセスできないだけということもあるわけです。
こうした忘却はどれも、脳が上手に機能するためのもので、私たちの祖先はそのおかげで生き延びてきました。
アルツハイマー病のような病気による忘却に問題がないというのではありません。
ただ忘却には進化的なメリットがあることを忘れてはいけません。
ですからあえて言うと、たまにうっかり物忘れをしても、それは進化上の利点の1つだと言う事です(笑)
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
1月24日の金曜日でございます。
最近、歳のせいか物忘れが激しすぎます。
買い物しようと町まで出かけたら、財布を忘れて、愉快なサザエさん現象をリアルで体験してしまったり、用事があって席を立ったはずなのに、何をしようとしていたのか忘れちゃうとかの現象が日常的に起こるようになってきました。
そんな物忘れは、多くの場合、ネガティブにとらえられがちですが、実は人間は、物忘れをするように進化をしてきたのだという説があります。
四六時中物忘れをするのはまた別の問題ですが、物忘れは、人間が生き延びるための生存戦略の1つなのだという話です。
では、いったいどんなメリットがあるのでしょう?
詳しく見ていきましょう。
トリニティ・カレッジ・ダブリンの神経科学者スヴェン・ヴァンネステ氏とエルヴァ・アルルチェルヴァン氏は、The Conversationで、忘れることの利点について説明してくれています。
19世紀のドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスは、人が物事を忘れる理由は、ただ単に記憶が薄れていくことが原因だと考えました。
彼が考案した「忘却曲線」によると、私たちが何かを新しく覚えたとき、その細かい部分はあっという間に忘れてしまいますが、その忘却速度は時間とともに緩やかになっていくという話です。
これは忘却についての初期の研究成果で、最近では神経科学的に再現されています。
ですが忘却は、ただの時間による記憶の風化というだけでなく、機能的な役割があると考えられています。
と言うのも、私たちの身の回りには洪水のように情報があふれているからです。
もしも、そのすべてを記憶しようとすれば、本当に大切な情報を記憶しておくことが難しくなるでしょう。
それを防ぐ方法の1つは、無視することです。
ノーベル賞受賞神経学者エリック・カンデル氏などによる研究では、記憶の形成を支えているのは、脳内の神経細胞同士のつながり(シナプス)の強まりであることを明らかにしています。
何かに注意を払うことは、シナプス結合を強化し、その記憶をより濃いものにすることにほかなりません。
ですから、それとは逆に注意を向けないことで、身の回りに溢れているどうでもいい情報を忘れることができるわけです。
新しい情報に対処するために、それまでの記憶が書き換えられ、それが忘却につながることもあります。
例えば、日々の通勤・通学では、いつもの道順をたどるでしょう。
するとその都度、脳の結合が強化され、その道順がしっかりと記憶されていくわけです。
ところが、ある日、道路の1つが通行止めになり、しばらく別の道を迂回せねばならなくなったとします。
この場合、新しい状況に対応するために、記憶を柔軟に修正してやる必要があるわけです。
そのためには一部の記憶結合を弱めて、新たな結合を強化します。
こうすることで新しい道順を記憶するわけなんです。
こうした記憶の更新ができなければ、困ったことになります。
例えば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、恐ろしい記憶を更新できず、それによっていつまでも苦しめられる症状です。
こうした記憶の柔軟さは、私たちの祖先の命を救ってきました。
例えば、狩猟採集生活を送っていた私たち祖先が、安全な水場を発見し、日々そこを訪れていたとしましょう。
ある日、そこで敵対する集落や危険な野生動物を発見しました。
この場合、彼らの脳は、水場がもう安全ではないと記憶を更新する必要があるわけです。
そうすることで、命を落としかねない危険から身を守ることができます。
じつは忘却の中には、単純に記憶が失われたことが原因でないケースもあります。
記憶自体はあるのに、そこにアクセスできなくて思い出せなくなっている場合があります。
たとえば、マウスによる実験では、忘れられたはずの記憶がシナプス結合を助けてやることで思い出されることが確認されています。
またアクセスできなくて思い出せないという経験は意外と身近なもので、何かの名前が喉元まで出かかっているというのに、思い出せないという経験は誰にもあるでしょう。
この現象は「舌先現象」とも呼ばれています。
1960年代にこれを研究した心理学者ロジャー・ブラウンとデビッド・マクニールは、名前を思い出せない人が、その名前の要素(たとえばSで始まる、短いなど)を特定できることに気がつきました。
これは情報が完全には忘れられていないことを告げているわけです。
舌先現象についての仮説によれば、思い出せないのは、名前とその意味を結びつける記憶結合が弱まったからであるという話です。
ですが別の可能性として、情報はきちんとあるのに、ただアクセスできないだけであることを伝えるサインとして機能しているとも考えられるそうなんです。
そう考えると、年齢を重ねて知識が増えた人ほど、舌先現象を経験しやすくなる理由をうまく説明できますね。
脳にたくさん情報がある人は、それらを整理して特定の情報を思い出すことが大変になります。
そこで脳が舌先現象を経験させて、「情報自体は消えていない、頑張れば思い出せるぞ」と告げているかもしれないんだそうです。
要するに、私たちが物事を忘れるのは、理由あってのことなのです。
情報を無視したり、時間とともに記憶が薄れたり、ときには記憶を更新するために、古い物事を忘れるかもしれません。
あるいは忘れたと思っていた記憶が、じつは忘れてはおらず、単にアクセスできないだけということもあるわけです。
こうした忘却はどれも、脳が上手に機能するためのもので、私たちの祖先はそのおかげで生き延びてきました。
アルツハイマー病のような病気による忘却に問題がないというのではありません。
ただ忘却には進化的なメリットがあることを忘れてはいけません。
ですからあえて言うと、たまにうっかり物忘れをしても、それは進化上の利点の1つだと言う事です(笑)
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院