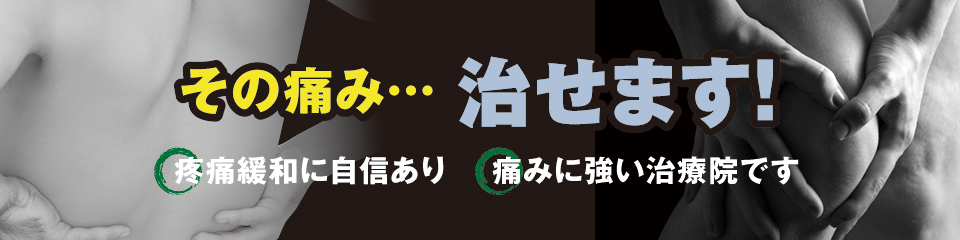2025年03月07日 [動物のこと]
光るキノコ
お疲れ様です。院長です。
3月7日の金曜日でございます。
何でも今日は「消防記念日」らしいですよ。
では元気にネタいきましょう。
キノコの世界に新たな光が灯りました。
すでに様々なキノコが生物発光されているのは知られていますが、日本でも見かける「アカチシオタケ」が、スイスの森で緑色に光っているのが確認されたそうなんです。
アカチシオタケはこれまで非発光性と考えられていましたが、人知れずひっそりと森の中で発光していたようなんです。
キノコの発光現象は長い間維持されているので、何らかの機能があると考えられますが、その詳細はまだ謎につつまれています。
「アカチシオタケ(Mycena crocata)」は、アジア、ヨーロッパ、北アフリカ、北アメリカなど世界各地に自生する「ラッシタケ科クヌギタケ属」の仲間です。
もちろん日本でもその存在が確認されています。
よく見られるのはブナをはじめとする紅葉樹の切り株や落ち葉で、夏から秋にかけて5〜15cmの細長いキノコをヒョロリと生やします。
根本は明るいオレンジ色ですが、先へと向かうにつれて淡い黄やクリーム色へと変化します。
ユニークなところは、傷をつけると濃いオレンジ色の浸出液を出すそうで、この点で、赤黒い浸出液を出すチシオタケとは大きく異なります。
また、カサの表面に放射状に入った条線がある事も特徴のひとつだそうです。
アカチシオタケの液の色は、料理に使われるサフランにも似ており、英名は「サフランドロップ・ボネット」というそうです。
アカチシオタケは無毒とされていますが、全体的に肉がついておらず味も美味しくない為、食用にされる事はないそうです。
ヤコウタケやツキヨタケなど、世界には100種以上の光るキノコが存在しますが、アカチシオタケは、これまで生物発光するとは考えられていませんでした。
スイスのアーティスト、ハイディ・バッゲンストス氏とアンドレアス・ルドルフ氏は、夕暮れの中、光るキノコを探すため、チューリッヒの森を散策していました。
そのときのことを両氏はこうニュースリリースで語っています。
わざわざ遠出しなくても、スイスの森にも生物発光するキノコが存在することを証明したいと思っていました。
キノコの生物発光は、肉眼ではわからないほど弱いことがあります。
そこでバッゲンストス氏らはカメラを覗きながら散策していたところ、そこに緑の光が映し出されたそうなんです。
最初、光るキノコは、すでに生物発光することが知られている「チシオタケ(Mycena haematopus)」だと思われていました。
ところがきちんと調べてみると、別種のアカチシオタケであることがわかったわけです。
その後、Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Researchの研究者、レナーテ・ハインツェルマン博士と共同で、アカチシオタケの生物発光を詳細に調査しました。
デジタル画像撮影や光電子倍増管を用いて、キノコの発光特性を調査し、そのゲノムに発光関連遺伝子を確認したわけです。
菌類が生物発光できるのは、「ルシフェラーゼ」という酵素のおかげです。
この酵素が「ルシフェリン」という発光化合物を酸化させる過程で、エネルギーが光として放たれると、怪しい緑色の光を放ちます。
今回の研究では、アカチシオタケのキノコは、根元以外ほとんど光らないことが明らかになっています。
光るのは、地下に植物の根のように張り巡らされている菌糸の部分でした。
ですが、そもそもキノコがなぜ光るのかよくわかっていません。
キノコが生物発光する理由は、昆虫を引き寄せ、胞子を広げてもらう可能性が推測されています。
ところが、クヌギタケの仲間の胞子は風に乗って飛びます。
またアカチシオタケは地下の菌糸しか光らないため、この仮説はうまく当てはまらないと思われます。
とは言え、生物発光の機能が今も失われずにあることから、まだ知られていない何らかの役割があるだろうと考えられているわけです。
まぁ、意味なく光ることはないでしょうし、きっとスゴイ役割があるんだと思いますけど、人間には気づけない何かなのかもしれませんね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
3月7日の金曜日でございます。
何でも今日は「消防記念日」らしいですよ。
では元気にネタいきましょう。
キノコの世界に新たな光が灯りました。
すでに様々なキノコが生物発光されているのは知られていますが、日本でも見かける「アカチシオタケ」が、スイスの森で緑色に光っているのが確認されたそうなんです。
アカチシオタケはこれまで非発光性と考えられていましたが、人知れずひっそりと森の中で発光していたようなんです。
キノコの発光現象は長い間維持されているので、何らかの機能があると考えられますが、その詳細はまだ謎につつまれています。
「アカチシオタケ(Mycena crocata)」は、アジア、ヨーロッパ、北アフリカ、北アメリカなど世界各地に自生する「ラッシタケ科クヌギタケ属」の仲間です。
もちろん日本でもその存在が確認されています。
よく見られるのはブナをはじめとする紅葉樹の切り株や落ち葉で、夏から秋にかけて5〜15cmの細長いキノコをヒョロリと生やします。
根本は明るいオレンジ色ですが、先へと向かうにつれて淡い黄やクリーム色へと変化します。
ユニークなところは、傷をつけると濃いオレンジ色の浸出液を出すそうで、この点で、赤黒い浸出液を出すチシオタケとは大きく異なります。
また、カサの表面に放射状に入った条線がある事も特徴のひとつだそうです。
アカチシオタケの液の色は、料理に使われるサフランにも似ており、英名は「サフランドロップ・ボネット」というそうです。
アカチシオタケは無毒とされていますが、全体的に肉がついておらず味も美味しくない為、食用にされる事はないそうです。
ヤコウタケやツキヨタケなど、世界には100種以上の光るキノコが存在しますが、アカチシオタケは、これまで生物発光するとは考えられていませんでした。
スイスのアーティスト、ハイディ・バッゲンストス氏とアンドレアス・ルドルフ氏は、夕暮れの中、光るキノコを探すため、チューリッヒの森を散策していました。
そのときのことを両氏はこうニュースリリースで語っています。
わざわざ遠出しなくても、スイスの森にも生物発光するキノコが存在することを証明したいと思っていました。
キノコの生物発光は、肉眼ではわからないほど弱いことがあります。
そこでバッゲンストス氏らはカメラを覗きながら散策していたところ、そこに緑の光が映し出されたそうなんです。
最初、光るキノコは、すでに生物発光することが知られている「チシオタケ(Mycena haematopus)」だと思われていました。
ところがきちんと調べてみると、別種のアカチシオタケであることがわかったわけです。
その後、Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Researchの研究者、レナーテ・ハインツェルマン博士と共同で、アカチシオタケの生物発光を詳細に調査しました。
デジタル画像撮影や光電子倍増管を用いて、キノコの発光特性を調査し、そのゲノムに発光関連遺伝子を確認したわけです。
菌類が生物発光できるのは、「ルシフェラーゼ」という酵素のおかげです。
この酵素が「ルシフェリン」という発光化合物を酸化させる過程で、エネルギーが光として放たれると、怪しい緑色の光を放ちます。
今回の研究では、アカチシオタケのキノコは、根元以外ほとんど光らないことが明らかになっています。
光るのは、地下に植物の根のように張り巡らされている菌糸の部分でした。
ですが、そもそもキノコがなぜ光るのかよくわかっていません。
キノコが生物発光する理由は、昆虫を引き寄せ、胞子を広げてもらう可能性が推測されています。
ところが、クヌギタケの仲間の胞子は風に乗って飛びます。
またアカチシオタケは地下の菌糸しか光らないため、この仮説はうまく当てはまらないと思われます。
とは言え、生物発光の機能が今も失われずにあることから、まだ知られていない何らかの役割があるだろうと考えられているわけです。
まぁ、意味なく光ることはないでしょうし、きっとスゴイ役割があるんだと思いますけど、人間には気づけない何かなのかもしれませんね。
ではまた〜。
京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院