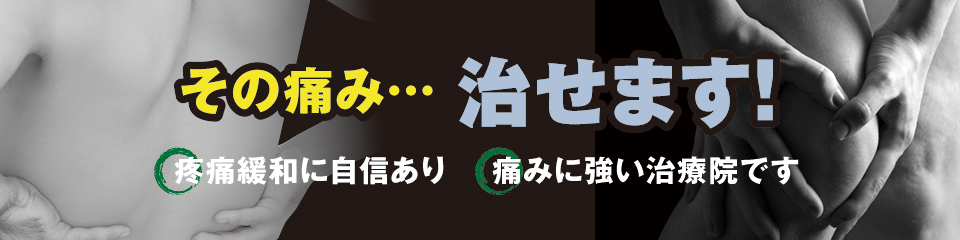2024年01月11日 [動物のこと]
ヒゲペンギンの睡眠
お疲れ様です。院長です。
1月11日の木曜日でございます。
1が3つ並びましたが、ポッキーでもプリッツでもなく、今日は「シャー芯の日」だそうです。
ではシャー芯に関係ないネタにいきましょう。
今日は動物ネタでございます。
主役はヒゲペンギンでございます。
このヒゲペンギンの独特な睡眠法についてお話ししたいと思います。
なんでもこのヒゲペンギン、4秒間のうたた寝を1万回繰り返して1日11時間睡眠を確保してるんだとか…。
南極大陸の周辺に生息するヒゲペンギンは、その名の通り、目の後ろから喉にかけてヒゲのような黒い模様があるのが特徴です。
過酷な環境の中を生きるヒゲペンギンは人間のようにゆっくり眠ってなんかいられません。
そこで独特な睡眠法を行っているわけです。
それが1日に平均わずか4秒という超短時間のマイクロスリープを1万回積み重ねて、必要とされる睡眠時間11時間以上を補っている可能性があるそうなんです。
最新の論文によりますと、この飛べない鳥は、絶えずまわりを警戒をしていなくてはならないことから、こうした特性を進化させたらしいんです。
アデリーペンギン属のヒゲペンギンは、ペンギンの仲間の中でももっとも生息数が多いとされている種類です。
現在、おもに南極大陸と南大西洋の島々に、およそ800万羽のつがいがいると想定されています。
つがいが営巣すると、パートナーがエサを探しに数日間出かけている間、もう片方はオオトウゾクカモメ、ワシなどの略奪者から卵を守るために、常に見張りを続けていなくてはなりません。
それだけではなく、仲間のペンギンに巣の材料を横取りされないよう監視もしなくてはならないんですな。
そして出かけていたパートナーが戻ってくると、この役割を交代します。
リヨン神経科学研究センターのポール=アントワーヌ・リブーレル氏率いる研究チームは、2019年12月にキングジョージ島のコロニーで14羽のヒゲペンギンに電極を埋め込んで、脳と首の筋肉の電気活動を記録しました。
それから、加速度計とGPSを使って、体の動きと位置を測定しました。
ビデオ録画と数日間にわたる直接観察データを組み合わせて、多くの独特な性質を特定することができたわけです。
立っているとき、寝そべって卵を抱いているときにペンギンたちは眠っていましたが、その平均睡眠時間はわずか3.91秒と…。
このマイクロスリープを1日に1万回以上繰り返していたそうなんです。
4秒×1万回…
つまり4万秒ってことですよね。
4万秒≒666分
666分≒11時間と…。
コロニーの端にいるペンギンは、中心部にいるペンギンよりも一回の睡眠時間は長く深かった。
この差は、コロニーの中心のほうが密集度が高く、巣の材料を盗られたりすることが多くなり、それに伴う大きな音や体のぶつかりあいが発生しやすいことからなんだとか…。
にしても、4秒って短いですよねぇ…。
一部の種では、こういった細切れ睡眠でも睡眠時間が確保できるようなんです。
こうした細切れ睡眠によって、ペンギンが実際にどれくらい子育ての疲労を回復しているかを実際に測定したわけではありません。
ですが、ペンギンたちの繁殖が成功していることから、神経細胞が沈黙している瞬間は、休息と回復のための手段になっていると考えることができるそうです。
今回の発見からは、これまで考えられていたこととは違って、少なくとも一部の種では、細切れ睡眠でも、それを多く行うことで必要な睡眠時間が確保できるようになったのだろうと言う事です。
ですが人間の場合は、このような細切れ睡眠は認知機能に影響を及ぼし、アルツハイマー病のような神経変性疾患を引き起こす可能性があるんだそうです。
たとえ人間目線では異常なことでも、少なくとも特定の条件下では、ペンギンやほかの動物にはまったく正常である場合があるわけですな。
まぁ、4秒とは言え、合計すると11時間寝てるわけですから、時短ってわけではないですもんね。
1月11日の木曜日でございます。
1が3つ並びましたが、ポッキーでもプリッツでもなく、今日は「シャー芯の日」だそうです。
ではシャー芯に関係ないネタにいきましょう。
今日は動物ネタでございます。
主役はヒゲペンギンでございます。
このヒゲペンギンの独特な睡眠法についてお話ししたいと思います。
なんでもこのヒゲペンギン、4秒間のうたた寝を1万回繰り返して1日11時間睡眠を確保してるんだとか…。
南極大陸の周辺に生息するヒゲペンギンは、その名の通り、目の後ろから喉にかけてヒゲのような黒い模様があるのが特徴です。
過酷な環境の中を生きるヒゲペンギンは人間のようにゆっくり眠ってなんかいられません。
そこで独特な睡眠法を行っているわけです。
それが1日に平均わずか4秒という超短時間のマイクロスリープを1万回積み重ねて、必要とされる睡眠時間11時間以上を補っている可能性があるそうなんです。
最新の論文によりますと、この飛べない鳥は、絶えずまわりを警戒をしていなくてはならないことから、こうした特性を進化させたらしいんです。
アデリーペンギン属のヒゲペンギンは、ペンギンの仲間の中でももっとも生息数が多いとされている種類です。
現在、おもに南極大陸と南大西洋の島々に、およそ800万羽のつがいがいると想定されています。
つがいが営巣すると、パートナーがエサを探しに数日間出かけている間、もう片方はオオトウゾクカモメ、ワシなどの略奪者から卵を守るために、常に見張りを続けていなくてはなりません。
それだけではなく、仲間のペンギンに巣の材料を横取りされないよう監視もしなくてはならないんですな。
そして出かけていたパートナーが戻ってくると、この役割を交代します。
リヨン神経科学研究センターのポール=アントワーヌ・リブーレル氏率いる研究チームは、2019年12月にキングジョージ島のコロニーで14羽のヒゲペンギンに電極を埋め込んで、脳と首の筋肉の電気活動を記録しました。
それから、加速度計とGPSを使って、体の動きと位置を測定しました。
ビデオ録画と数日間にわたる直接観察データを組み合わせて、多くの独特な性質を特定することができたわけです。
立っているとき、寝そべって卵を抱いているときにペンギンたちは眠っていましたが、その平均睡眠時間はわずか3.91秒と…。
このマイクロスリープを1日に1万回以上繰り返していたそうなんです。
4秒×1万回…
つまり4万秒ってことですよね。
4万秒≒666分
666分≒11時間と…。
コロニーの端にいるペンギンは、中心部にいるペンギンよりも一回の睡眠時間は長く深かった。
この差は、コロニーの中心のほうが密集度が高く、巣の材料を盗られたりすることが多くなり、それに伴う大きな音や体のぶつかりあいが発生しやすいことからなんだとか…。
にしても、4秒って短いですよねぇ…。
一部の種では、こういった細切れ睡眠でも睡眠時間が確保できるようなんです。
こうした細切れ睡眠によって、ペンギンが実際にどれくらい子育ての疲労を回復しているかを実際に測定したわけではありません。
ですが、ペンギンたちの繁殖が成功していることから、神経細胞が沈黙している瞬間は、休息と回復のための手段になっていると考えることができるそうです。
今回の発見からは、これまで考えられていたこととは違って、少なくとも一部の種では、細切れ睡眠でも、それを多く行うことで必要な睡眠時間が確保できるようになったのだろうと言う事です。
ですが人間の場合は、このような細切れ睡眠は認知機能に影響を及ぼし、アルツハイマー病のような神経変性疾患を引き起こす可能性があるんだそうです。
たとえ人間目線では異常なことでも、少なくとも特定の条件下では、ペンギンやほかの動物にはまったく正常である場合があるわけですな。
まぁ、4秒とは言え、合計すると11時間寝てるわけですから、時短ってわけではないですもんね。