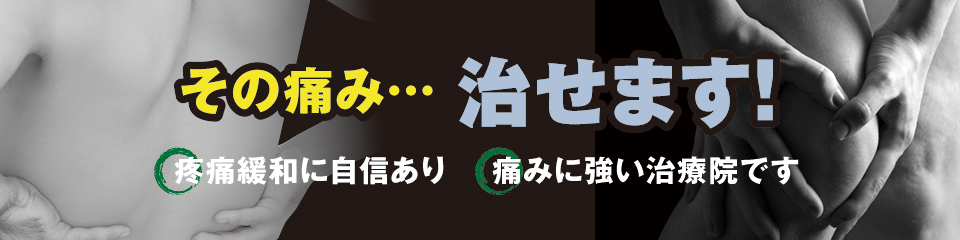2016年06月22日 [動物のこと]
同性愛、どうせいっちゅうねん。
お疲れ様です。院長です。
6月22日水曜日。
一番元気な火曜日から、一日たってちょっと疲れた水曜日ってとこですかね。
今日も頑張っていきましょう。
昨日は、お亡くなりの特殊な形、脳死についてのお話でしたが、今日は真逆の生まれる時の特殊な話…
生まれると言えば、当然ながら生殖活動が行われ、そして種が受け継がれていくわけですが、その生殖活動のお話いってみよ。
ちょっと驚きなんですが、鳥やミツバチ、ペンギン、ライオンやキリンなど、自然界では以外にも、同性愛が普通に存在するんですって。
知ってました?
私は知らなかったです〜
じゃ、なぜ動物に同性愛が存在するのか?
その理由は進化上の謎とされてきたそうなんですが、最近の研究で同性愛行為に遺伝的な利点があることが明らかになったらしいのです。
遺伝的な利点?
つまりは、種を繁栄させていくにあたって、同性愛が存在する方が得ってことですかね…
かのチャールズ・ダーウィンは、動物の性衝動は生殖を促すようできており、それゆえに必ず異性愛になると考えました。
しかし、自然界にはかつて専門家が一部の例外として否定してきた同性愛が、それまで考えられていた以上に普通に存在することが明らかとなりつつあるみたいなんです。
一部の例外(笑)
ま、一応、際物扱いですが、あるにはあったってことですね。
で、実際にはエミュー、鶏、コアラ、サケ、猫、フクロウ、イルカなど、自然界の同性愛は1,500種で目撃されており、そのうち3分の1できちんと信頼の置ける記録が取られているそうなんです。
スウェーデン、ウプサラ大学の生態遺伝学科の研究者は、一方の性では発現すると同性愛を促す遺伝子が、他方の性で発現すると別のメリットがある場合に、同性愛が起きるのではないかと仮説を打ち立てました。
で、ここから仮説を検証するために、低レベルの同性愛行為が確認されたマメゾウムシのオスとメスで実験が行われたそうなんですね。
マメゾウムシ…
知ってます?
↓こいつですわ

うちの副院長はご存知でした。豆を食べるから、「マメゾウムシ」っていうんですって。
そしてこの画像のは「アズキマメゾウムシ」やて。
あと、「コクゾウムシ」とかも仲間でいるそうです。
そう、穀物を食べるから「コクゾウムシ」
ひとつ賢くなったねぇ…
で、話を戻して、まずマメゾウムシで人工交配を行い、同性愛傾向のある遺伝子グループを作成します。
つまり、何となく同性同士で集まる傾向のある個体たちを集めて繁殖させると…
すると、この同性同士で集まった遺伝子グループでは、その個体の異性のきょうだいに繁殖力が高いことが判明したようなんです。
つまり、同性同士のマウンティング行動を強化されたオスにおいて、後のテストで求愛行動を確かめた際に、オスとメスとで特に区別している様子はなかった(つまりバイですね。)一方で、そのきょうだいであるメスでは通常よりも多くの産卵が確認されたということです。
この結果は、同性愛行為が一方の性に広まるのは、異性側にメリットがあり、その行動を司る遺伝子が自然選択によって保存されるからであるという説を裏付けているらしいです。
これは幅広い動物種で同性愛が見られる基本メカニズムを示しているんだって。
要するに…
きょうだい(仮に姉と弟としましょう)のうち、弟がゲイなら、姉ちゃんは繁殖力がすごいってことやろか…
んん〜…
これが本当なら、確かに種の繁栄にメリットあるっちゃあるよねぇ…
専門家によれば自然界における同性愛の研究は、長い間タブー視されてきたといいます。しかし、性は繁殖のみならず、群れの機能を円滑にするという役割もあるために、非常に重要なテーマだと言えます。
例えば、部族単位で生活する動物では、あぶれたオスを満足させたり、オス同士の絆を強化するなど、社会的な機能を果たすことがあるそうですから…
2010年にオアフ島で実施されたハワイ大学の調査では、対象となったおよそ120羽のアホウドリの多くが、同性愛的行動をとっていることが明らかとなったそうです。
つがいの3分の1はメス同士であり、DNA解析から一部のメスは最大19年間もつがいであり続けていることが判明したらしいです。どうやらメスは父親となるオスを探す(つまり交尾する)が、その後は同性であるパートナーの元に帰り、卵を温めていると…
これはなかなか凄いですね。
この場合のオスは、単純に生殖行動のためだけに存在しています。
そして、その行為が終わったらもう用なしってことですもんねぇ…
まぁ、これが良いか悪いかは別として、私は今まで、動物は本能で生殖し、それに伴い群れを形成してるもんだと思ってましたが…
それだけじゃないんですねぇ…
こういった新しい発見を経て、色々な生態系が解明されてくんやろねぇ〜
てことで、今日は同性愛について熱く論じてみました。
ではまた〜

京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院
6月22日水曜日。
一番元気な火曜日から、一日たってちょっと疲れた水曜日ってとこですかね。
今日も頑張っていきましょう。
昨日は、お亡くなりの特殊な形、脳死についてのお話でしたが、今日は真逆の生まれる時の特殊な話…
生まれると言えば、当然ながら生殖活動が行われ、そして種が受け継がれていくわけですが、その生殖活動のお話いってみよ。
ちょっと驚きなんですが、鳥やミツバチ、ペンギン、ライオンやキリンなど、自然界では以外にも、同性愛が普通に存在するんですって。
知ってました?
私は知らなかったです〜
じゃ、なぜ動物に同性愛が存在するのか?
その理由は進化上の謎とされてきたそうなんですが、最近の研究で同性愛行為に遺伝的な利点があることが明らかになったらしいのです。
遺伝的な利点?
つまりは、種を繁栄させていくにあたって、同性愛が存在する方が得ってことですかね…
かのチャールズ・ダーウィンは、動物の性衝動は生殖を促すようできており、それゆえに必ず異性愛になると考えました。
しかし、自然界にはかつて専門家が一部の例外として否定してきた同性愛が、それまで考えられていた以上に普通に存在することが明らかとなりつつあるみたいなんです。
一部の例外(笑)
ま、一応、際物扱いですが、あるにはあったってことですね。
で、実際にはエミュー、鶏、コアラ、サケ、猫、フクロウ、イルカなど、自然界の同性愛は1,500種で目撃されており、そのうち3分の1できちんと信頼の置ける記録が取られているそうなんです。
スウェーデン、ウプサラ大学の生態遺伝学科の研究者は、一方の性では発現すると同性愛を促す遺伝子が、他方の性で発現すると別のメリットがある場合に、同性愛が起きるのではないかと仮説を打ち立てました。
で、ここから仮説を検証するために、低レベルの同性愛行為が確認されたマメゾウムシのオスとメスで実験が行われたそうなんですね。
マメゾウムシ…
知ってます?
↓こいつですわ

うちの副院長はご存知でした。豆を食べるから、「マメゾウムシ」っていうんですって。
そしてこの画像のは「アズキマメゾウムシ」やて。
あと、「コクゾウムシ」とかも仲間でいるそうです。
そう、穀物を食べるから「コクゾウムシ」
ひとつ賢くなったねぇ…
で、話を戻して、まずマメゾウムシで人工交配を行い、同性愛傾向のある遺伝子グループを作成します。
つまり、何となく同性同士で集まる傾向のある個体たちを集めて繁殖させると…
すると、この同性同士で集まった遺伝子グループでは、その個体の異性のきょうだいに繁殖力が高いことが判明したようなんです。
つまり、同性同士のマウンティング行動を強化されたオスにおいて、後のテストで求愛行動を確かめた際に、オスとメスとで特に区別している様子はなかった(つまりバイですね。)一方で、そのきょうだいであるメスでは通常よりも多くの産卵が確認されたということです。
この結果は、同性愛行為が一方の性に広まるのは、異性側にメリットがあり、その行動を司る遺伝子が自然選択によって保存されるからであるという説を裏付けているらしいです。
これは幅広い動物種で同性愛が見られる基本メカニズムを示しているんだって。
要するに…
きょうだい(仮に姉と弟としましょう)のうち、弟がゲイなら、姉ちゃんは繁殖力がすごいってことやろか…
んん〜…
これが本当なら、確かに種の繁栄にメリットあるっちゃあるよねぇ…
専門家によれば自然界における同性愛の研究は、長い間タブー視されてきたといいます。しかし、性は繁殖のみならず、群れの機能を円滑にするという役割もあるために、非常に重要なテーマだと言えます。
例えば、部族単位で生活する動物では、あぶれたオスを満足させたり、オス同士の絆を強化するなど、社会的な機能を果たすことがあるそうですから…
2010年にオアフ島で実施されたハワイ大学の調査では、対象となったおよそ120羽のアホウドリの多くが、同性愛的行動をとっていることが明らかとなったそうです。
つがいの3分の1はメス同士であり、DNA解析から一部のメスは最大19年間もつがいであり続けていることが判明したらしいです。どうやらメスは父親となるオスを探す(つまり交尾する)が、その後は同性であるパートナーの元に帰り、卵を温めていると…
これはなかなか凄いですね。
この場合のオスは、単純に生殖行動のためだけに存在しています。
そして、その行為が終わったらもう用なしってことですもんねぇ…
まぁ、これが良いか悪いかは別として、私は今まで、動物は本能で生殖し、それに伴い群れを形成してるもんだと思ってましたが…
それだけじゃないんですねぇ…
こういった新しい発見を経て、色々な生態系が解明されてくんやろねぇ〜
てことで、今日は同性愛について熱く論じてみました。
ではまた〜

京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院